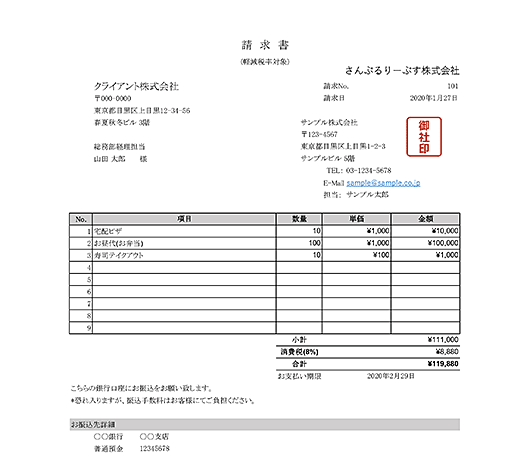目次
[非表示]
こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。注文書を発行する際には、基本を把握しておく必要があります。注文書の意味や目的、発行が義務となるケースを知ることが主なポイントです。本記事では注文書とはどんな書類なのか、その基本について解説します。
参考:注文書とは?社会人が知っておきたい注文書の基本事前に下請法の対象になる取引の内容を把握し、理解を深めておく必要があります。
注文書とは何か?
注文書という名称を聞いたことがあっても、その詳細を知らないケースもあるかと思います。以下では、注文書の基本について解説します。注文書とは取引先に「発注すること」を伝える書類
注文書とは、取引先に「発注すること」を伝える書類のことを指します。注文書を発行することで、具体的な取引を進めることが可能となります。発注する側の企業は注文書の役割を理解し、スムーズに発行できる環境を構築することが必要です。注文書が必要になるシーン
注文書は材料の仕入れ時や、外注先に仕事を発注する際に必要となる書類です。注文書を作成して具体的な金額や内容を明記することで、取引を成立させられます。注文書がないままの口約束では、あとから契約金額や納品の数量などに齟齬が生まれるリスクがあります。取引先も注文書がないことで不安を覚える可能性が高いため、基本的に仕入れや仕事の発注時には注文書を発行できるように備えましょう。注文書と発注書の違いとは?
注文書と同様に、発注書も事業上で必要になる重要な書類です。以下では、注文書と発注書の違いについて解説します。注文書と発注書に違いはない
注文書と発注書は、基本的には同じ役割をもつ書類です。先に解説したように、材料の仕入れの際や外注先に仕事を任せる際の、発注内容を記載する書類として、発注書を発行します。同じ役割を持つ書類となるため、意味もなく両方を使っていると職場に混乱を招く恐れがあります。事前に社内で名称を統一し、注文書と発注書のどちらか一方だけを使うように制度を整える方法がおすすめです。企業によっては、明確に注文書と発注書を使い分けている例もあるため、取引先企業から要望があった場合には、適宜注文書と発注書を使い分ける必要もあります。注文書を発行する目的・理由
以下では、注文書を発行する目的・理由について解説します。注文書で取引の内容を明確にする
注文書を発行することで、取引の内容を明確にできます。注文書のない口約束だと、後から数量や金額が正しいか確認することが難しくなります。そのため事前に注文書を発行して、発注した証拠を残すのが主な目的です。注文書にミスがあると証拠として利用できないため、発行時には細かなチェックを欠かさないようにしましょう。「下請法」の対象となる取引では注文書の交付が義務付けられている
「下請法」の対象となる取引では、注文書の交付が義務付けられています。以下では、下請法と注文書の関係性を解説します。下請法には注文書の発行や記載内容が定められている
下請法には、注文書の発行や記載内容が定められています。例えば下請法では、「納品から60日以内かつ迅速な支払い義務」が定められています。下請け企業が不当な扱いを受けないように、さまざまな条件・ルールが制定されています。万が一支払いに遅延した場合、下請法に則って利息の支払い義務も発生します。下請法の対象となる取引の際には、注文書の発行および記載内容を十分に確認した上で契約に進む必要があります。下請法の対象になる取引の内容
下請法の対象になる取引には、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務委託」などがあります。これらに加え、取引事業者の資本金が定められた要件に当てはまるかどうかで、下請取引になるかが決まります。具体的には資本金の金額によって、以下のような内容となります。| 取引の種類 | 親事業者 | 下請事業者 |
| ・物品の製造委託・修理委託・情報成果物委託・役務提供委託 | 資本金が3億円を超える法人 | 資本金が3億円以下の法人、もしくは個人事業主 |
| 資本金が1,000万円を超えて、3億円以下の法人 | 資本金が1,000万円以下の法人、もしくは個人事業主 | |
| ・情報成果物委託・役務提供委託 | 資本金が5,000万円を超える法人 | 資本金が5,000万円以下の法人、もしくは個人事業主 |
| 資本金が1,000万円を超えて、5,000万円以下の法人 | 資本金が1,000万円以下の法人、もしくは個人事業主 |