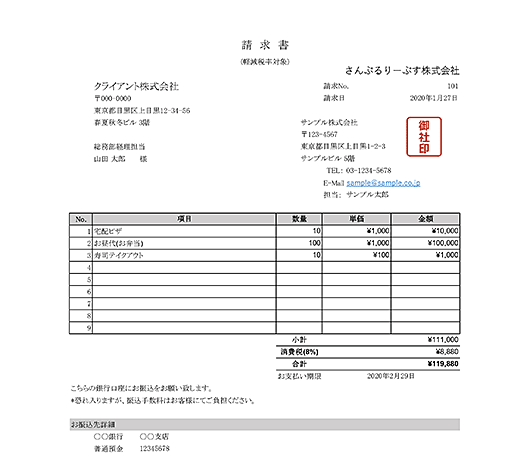目次
[非表示]
こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。請求書や納品書、見積書といった取引先に発行する各種書類の作成に、Excel®(エクセル)などの表計算ソフトを利用されている企業も多いのではないでしょうか。表計算ソフトを使う理由としてよくあるのは、「使い慣れている」、「費用が安価」などが多いと存じます。一方、作業負担の削減や事業活動上のリスク低減などを目的として、取引書類の作成・管理に使うツールを表計算ソフトから専用ソフトに切り替えるケースをよく耳にします。本記事では、Excel®(エクセル)をはじめとする表計算ソフトによる請求書や見積書の作成・管理にやや不安を感じているという方に向けて、「なぜ表計算ソフトによる書類作成・管理をやめる企業が増えているのか?」を解説します。本記事をご覧いただくことで、以下の内容をご理解いただくことができます。
- 表計算ソフトで請求書等の取引書類を作成・管理するメリットとデメリット
- なぜ、表計算ソフトでの書類作成・管理をやめる企業が増えているのか?
- どのように表計算ソフトから脱却すればいいのか?
- 表計算ソフトから専用ソフトに移行する方法
表計算ソフトで請求書等の取引書類を作成・管理するメリットとデメリット
表計算ソフトとは
まず表計算ソフトとは、表形式で各種データの集計や分析等を行うツールの総称です。具体的なソフトとしては、Excel®(エクセル)やGoogle スプレッドシート等が表計算ソフトに該当します。前述の通り、表計算ソフトは各種数値データの計算をすることに特化したツールとなりますが、文字入力やレイアウト調整等ができることから、請求書や納品書、見積書等の取引書類作成に利用されることがあります。表計算ソフトを使うメリット
ここからは各種取引書類の作成に、表計算ソフトを使うメリットを紹介していきます。使い慣れている
メリットの1点目は、「使い慣れている」という点です。表計算ソフトは業務で利用するPCにプリインストールされている場合も多く、(取引書類の作成以外の用途で)日常的に利用されている方も多いのではないでしょうか。(既に利用料を支払っていれば)追加コストはかからない
2つ目のメリットとしては、取引書類の作成以外の用途で既に表計算ソフトを利用していれば(利用料を支払っていれば)、追加のコストが発生しないという点です。(表計算ソフトの知識が豊富であれば)作業を効率化できる
表計算ソフトに詳しく、関数やマクロ等の知識が豊富であれば、取引書類の作成業務を効率化できるという点もメリットです。関数やマクロを使うことで、表計算ソフトへの手入力作業を減らし、ある程度作業を効率化することができます。表計算ソフトを使うデメリット
ここからは、表計算ソフトを取引書類の作成に利用することのデメリットを解説します。属人化しやすい
まず1つ目は、書類の作成や管理の方法が属人化しやすいという点です。表計算ソフトでは書類レイアウトを自由に変更できることから、社内の担当者ごとに異なるフォーマットで顧客に書類を提出してしまうといったことが発生します。また、データの保存・共有に関する運用が徹底されていないことで、書類データが個人のPCに保存され、必要な時にすぐにデータを確認できないといったことも起こりがちです。手入力が多く作業負荷が大きい
表計算ソフトでの書類作成は、(知識が豊富で作業を自動化できている場合を除き)商品や金額などの手入力が発生し、作業負荷が大きくなりがちです。書類を1件作成する時間はそこまで気にならなくても、その作業を毎月続けることで、多くの時間を費やすことになってしまう点は改善余地があります。手作業によるミスが発生しやすい
手入力・手作業が多くなることの弊害として、人的ミスが発生しやすいという点も挙げられます。また、ミス防止のために作成した書類の内容を確認する作業も、業務時間が増えてしまう一因となります。なぜExcel®(エクセル)などの表計算ソフトを使った請求書・見積書作成をやめる企業が増えているのか?
ここからは、なぜ表計算ソフトを使った取引書類の作成・管理から脱却する企業が増えているのかを解説していきます。端的に言えば、前章に記載したデメリットの回避(属人化・作業負荷の増大・ミスの発生等)が主な理由になります。これらのデメリットは作業面における弊害と言えますが、これらを放置することが「事業活動上のリスク」になると捉える経営者(または業務の管理責任者)が多いと思われます。ここで言う「事業活動上のリスク」とは、たとえば以下のような点です。- 社員が事務作業に多くの時間を割くことで、売上を伸ばすための活動に割く時間が減少
- 書類データの共有が十分でないことで、スピード感のある顧客対応ができず、顧客満足度が低下
- 法律の要件に沿った書類作成・保存ができず、企業としての信頼性が低下(法律の例:インボイス制度、電子帳簿保存法)
- コピー&ペーストや金額の手入力といった手作業が多くなることで、書類作成にミスが発生し、取引先からの信用が低下
- 事務作業の負荷が大きいことで、社員のストレスが増大し、仕事への満足度が低下
- 書類の承認ルールが徹底されていないことで、不正やトラブルが発生
- 案件や顧客の情報が個人管理になっていることで(属人化)、担当変更時または退職時のリスクが増大
どのように表計算ソフトから脱却すればいいのか?
ここまで、取引書類の作成・管理業務における表計算ソフトの利用をやめる企業が増えている理由を解説してきました。ここからは、表計算ソフトをやめる具体的な方法を解説していきます。その方法として一般的なのは、専用ソフト(書類作成・管理サービス)を使う、という方法です。もちろん、専用ソフトの利用にあたっての費用は発生しますが、初期費用0円、月額費用1,000円ほどで始められるソフトもあります。前章に記載した事業活動上のリスクや不安を解消することと天秤にかけると、非常に安価と捉えることもできるのではないでしょうか。表計算ソフトから専用ソフトに移行する方法
ここからは、Excel®(エクセル)をはじめとする表計算ソフトから専用ソフトに移行する具体的な方法を解説します。ステップとしては、以下2つのステップで進めることが一般的です。①現状の把握・整理 ②サービスの情報収集ここからは、それぞれのステップの詳細について解説します。①現状の把握・整理
まず最初のステップ①では、自社の業務や抱える課題にマッチするサービスを選定するために、現在の業務を把握・整理します。具体的には以下2つのポイントをおさえましょう。- 取引書類の作成~発送、請求後の入金管理まで、業務の流れを整理
- 業務の課題を整理した上で、優先課題をつける
- バラバラな書類フォーマットの統一
- 作成した書類データの共有、可視化
- コピー&ペーストや金額の手入力等によるミスの削減
- 書類郵送作業(印刷・紙折り・封入作業など)の負荷低減
- 入金消込にかかる作業負荷の削減
②サービスの情報収集
次にステップ②では、専用ソフトの情報収集をします。情報収集をする際は、以下のような観点で情報収集することをおすすめします。- 機能(自社の業務や課題に合った機能を有しているか)
- 料金(実現できることと料金のバランス)
- サポート(導入前・後のサポートは十分か)
- 信頼性(中長期的に安心して利用できそうか)